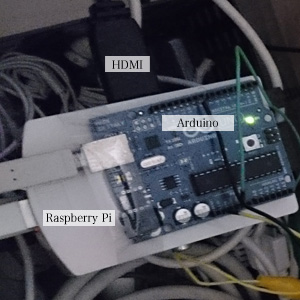現金が使えない自動販売機「イノベーション自販機」を使ってみる
 イノベーション自動販売機
イノベーション自動販売機
まずは、どこにこの自販機があるのか確認するためにスマートフォンアプリ、acureをインストール。
インストールに続いて、初期設置が、終わったら、まずどこにこの自販機があるか確認。
東京駅内だと2つ程あるようだ。
さて、「いざ購入」と行きたい所だが、アプリ内で購入するのには、決済方法の登録が必要だ。
Suicaで使用しようかと思ったが、メアドなんだっけと、続いてLINE PAY、これもパスワードなんだっけ?というわけで、結局クレジットカードを選択。
もちろん、電子マネー専用自販機のように、商品を選択して、ピッとやれば、その場で商品の購入可能だ。
ただ、この自販機が、他と違うのは、先にスマホで購入した商品を、自販機で受け取る事ができるという点だ。
要は、あらかじめオンラインで商品を購入して、必要な時にそれを最寄りの自販機から受け取るという想定になっているのだ。
そのため、この自販機は在庫数を管理しており、専用アプリから在庫があるか確認できる。
・ネットショップだと、在庫があるかどうかは確認できるが、届くまでに時間がかかる。
・リアル店舗だと、在庫があるかどうかは、電話で確認するか、行かないとわからない。
とまあ、少し前から言われているO2Oを具現化したような仕組みなのだ。
しかも、まとめて購入で割引なんていう買い方もある。
これまで、商品をまとめ買いするとお買い得です。という売り方はあったが、
その場合は、購入した時点で一気に受け取る仕組みしかなく、
1ヶ月でみると同じ商品を1ダース買ったと同じだけれど、まとめ買いによる
恩恵をうけれなかった。
私の場合、ペットボトル飲料を時々購入するのだが、コンビニで買うより、箱買いしてストックしておくと、ちょっとお得なので、たまに箱買している。
なのでこの、「必要な時に必要な分をうけとる」という、ボトルキープ的な発想は、なかなか良い仕組みだと思う。
そう考えると、このイノベーション自販機は、「Amazon GO」か、ある意味、それより一歩進んだサービスと考えてもよいかもしれない。
もちろん、この仕組みにも課題はある。
受け取れる自販機が身近になければ、受け取れないし、購入しておいた商品が、
在庫切れや、販売終了になった場合、内容物が変化した場合、どのような対応になるかなど、どのようなルールになっているか把握できてない点もある。
ともかくまあ、アメリカの、レジなしコンビニ「Amazon GO」が注目されているが、
このイノベーション自販機は、結構革新的な仕組みだと思う。
返品こそはできないが、
・事前に支払いも可能、その場でも電子マネーで購入可能。
・外から在庫が確認できる。
・まとめ買いの恩恵を受けれる。
ペットボトルや、缶入りだけじゃなくて、もっと幅広い商品になれば、
コンビニ的なサービスの無人化もしくは、少人数化につながるだろう。
ちなみに、今回、決済方法の設定で手こずって自販機の近くにいた間、
現金で買おうとして、「あれ現金使えないのか」と、他の自販機に行く人や、「あ現金使えないんだ、じゃSuicaで」とSuicaで買っている人がいた。
電子マネーのメリットは、
・集金する手間や、釣り銭を補充が省ける。
・自販機内の現金を狙った、強盗や、ニセ硬貨による不正使用が減るかもしれない。
・小銭詰まりなど、投入部分の故障は発生しなくなる。
などがあげられる。
現金しか持ってないというケースもあるかもしれないが、
電子マネー専用の改札機同様で、ある程度仕方がないし、ある程度は増やして行くのが正しいと思う。
acure自動販売機 | エキナカ自販機 acure<アキュア>